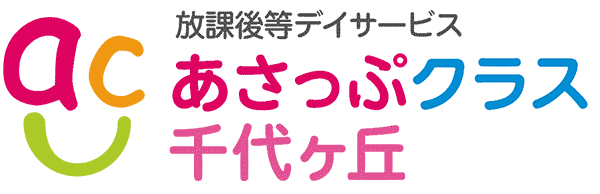「療育」
と、一口に言っても、実に様々な方法やツールを用いたものがあります。
発達障害や、障害を持つ子どもたちにとって発達を促すことに有用なものは、全て「療育」に繋がります。
幼いころから、子どもが自然と手を伸ばし、進んで取り組むことができるもので療育ができるととてもいいですよね。
そんなツールある?
と、お思いの方もいるかもしれませんが、あります。笑
それは、「おもちゃ」です。
おもちゃといっても、多種多様ありますが、乳幼児向けになってくると五感、特に触覚、視覚、聴覚をよく使うものが、療育にも効果的です。
代表的なものが、ブロック。
平面に並べること。同じもの同士でそろえること。立体的に組み立てること。遊び方は無限大です。
また、「知育玩具」として紹介されているものもあり、より子どもたちが考え、工夫次第では遊び方が無限大に広がるおもちゃもあります。
知育を目的としたおもちゃは、もちろん子どもも楽しいですし効果も見込まれますが、高価なものも多いです。笑
その分、普通のおもちゃでも療育としての正しい知識と養わせたい能力を明確に理解できてさえいれば、立派な知育玩具になりえます。
では、知育玩具として取り扱う場合、上記ではブロックを例に出しましたが、実際にどのような要素が含まれているおもちゃを選べばいいのでしょうか。
まず、第一に考えるべき点は、「安全」であることです。どんなに楽しく遊べるおもちゃだとしても、怪我をしてしまうようなものは子どもも親も安心して遊ぶことはできません。手で触ること、口に入れてしまうこと、投げてあたってしまうこと、色々なことが想定されますが、どのようなことがあっても「安全」に遊ぶことができることが重要です。
次に、子どもにどのようなことを養わせたいか、ということ明確にすると、療育では、「手先の器用さ」「集中力」「視る力(視空間認知うや追従性眼球運動)」「創造力」というところを念頭において、選ぶことをおすすめします。
百円均一で売っているようなパズルなどは、「手先の器用さ」や「集中力」を養うのにうってつけです。
大きなブロックなどは、パズルで養える力に加え「創造力」が養われます。
ボールや玉などが動くおもちゃなどは、「視る力」を養うことができます。
このように、どのような能力を養わせたいかを正しく明確に理解できていれば、どんなおもちゃでも「知育玩具」に早変わりです。
そして、その効果が二倍にも三倍にも効果が向上するのは、親が一緒に楽しそうに遊ぶ、ということが必要不可欠です。
小さいうちからおもちゃで遊ぶことは、子どもの想像力を広げ、また、一人でも遊ぶことができ、親の負担も少なくなるという側面もあります。
是非、普通のおもちゃを「知育玩具」として、子どもの療育ツールに活かしてみてはいかかでしょうか。