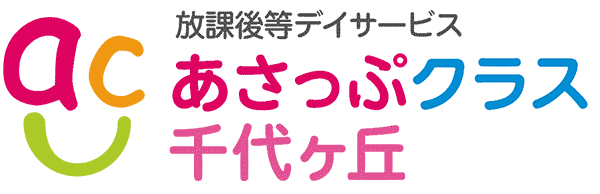発達障害は、社会の中で年々認知し始めています。
子どものうちから、発達の課題に応じた正しい療育を行うことで、子ども達の生きづらさを少しでも無くすことが出来ます。
しかし、発達障害は現時点で完全に治るというものではなく、症状や傾向として向き合っていかなければいけないものでもあります。
大人になったときに向き合い始めるのではなく、幼いころから、家族や周囲のサポートを受けながら、自分自身の特性を理解して、将来のビジョンを作っていくことが生きやすさに繋がっていきます。
今回は、発達障害を持っている方に向いている職業について書いていきます。
<ASD(自閉症スペクトラム)について>
ASD(自閉症スペクトラム)を持つ人達にとって、仕事に就くときの一番のハードルは、コミュニケーションを取ることです。
独特なコミュニケーション方法を要する場合が多いASD傾向の人は、いわゆる「場の空気を読む」ということが苦手です。
変な軋轢を生んだり、誤解が生じたりして仕事自体に苦しさを感じる場合があります。
ASD傾向の人たちに向いているのは、コミュニケーションを必要としない職業。自分のペースで出来る仕事、などがいいと言われています。
例として挙げると、職人的な仕事、研究者、プログラマーなどのコンピュータ関連の仕事など、コミュニケーションが全く必要というわけではないですが、比較的一つのことに集中して取り組むことが出来る仕事が向いていると言えます。
逆に言えば、コミュニケーションを要し、マルチタスク能力を要する仕事など臨機応変さの必要な職業はあまり向いていないでしょう。
例としては、接客業や営業職、教師などが言えます。
実際に、これまでの歴史の中で発達障害を持ちながら仕事に就き、大成した人もたくさんいらっしゃいます。
アメリカのテンプル・グランディンという女性がその一人です。
彼女は、高機能自閉症でありながら動物学者として活躍しています。
その中でも彼女の一番の功績は、アメリカの食肉工場施設の1/3もの施設に取り扱われている設備の設計をしたことです。
彼女がいち早く取り入れた施設としての設計は、その後、アメリカ全土に広がり、動物にとっても従業員にとっても作業効率が上がり、工場としてのプロセスと品質の改善につながったのです。
テンプル・グランディンが持っているであろう、感覚過敏、そして特有の視空間認知能力、また好きな動物のことを突き詰めていく中でわかる動物の目線や感覚といったものが養われた結果、このような功績を残すことが出来たのではないでしょうか。
テンプル・グランディンはASD(自閉傾向)にある子ども達の【こだわりを広げること】を自身の講演で述べています。
こだわりを持っていることに関連させて、色々な方法や考え方を実践させてみる。
「子ども達のスイッチを入れる」ということが重要なのだと。
自分自身と向き合い、また周囲の人たちと話をしたりして、子どものうちから能力開発をしていくことが発達障害を持っている人のみならず、生きづらさを生きやすさに変えていくことが出来そうですね!
ADHD傾向の人の向いている仕事に関しては、また次回書いていきます。