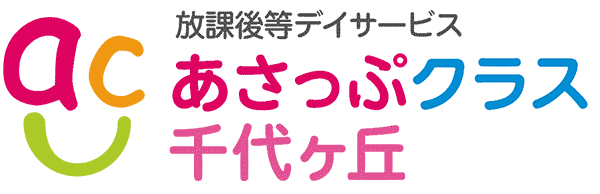注意欠陥多動性障害(Attenntion Deficit Hyperactivity Disorder :ADHD)は、不注意(注意散漫)、多動性、衝動性を特徴とする発達障害です。
不注意とは、周囲の刺激に敏感に反応する、1つのことを最後までやりきることが難しいなどの注意継続の困難。
多動性とは、座席にじっと座り続けることが難しい、話し出すと止まらないなどの運動調節の困難。
衝動性とは、順番を待てない、思ったことをすぐに声に出すなどの行動抑制の困難です。
行動開始のアクセルを踏むことには問題がないのですが、アクセルを緩めたり、ブレーキに踏みかえることが苦手だということです。
ADHDの基本的な原因は、中枢神経系の障害です。
小・中学校の通常学級に在籍する児童生徒の約3%がADHDを疑われるといわれていますが、医学的に診断された数ではないので注意が必要です。
また、行動のようすから3つのタイプに分けられます。
1つ目は不注意優勢型で、多動性や衝動性を示さず、不注意のみが認められるタイプです。
2つ目は多動性衝動性優勢型で、多動性や衝動性は示しますが、不注意はあまり認められません。
3つめは混合型で、不注意、多動性、衝動性の3つ認められるタイプです。
この中で、不注意優勢型は見落とされがちです。
日常生活での暴言や離席などの目立った行動がないため、発見が遅れることがあります。
授業をしっかり聞いているように見えても、周りの刺激に注意を取られ、授業に集中できていないかもしれません。
発見が難しいだけに、ていねいな実態把握と支援、配慮が必要です。
ADHD児は、周囲の刺激に注意を奪われがちです。集中しやすい環境を周りにいる支援者が用意することが大切です。
1つ目は、課題を行うときに刺激をできるだけ取り除くことです。
机の上にはキャラクターが描かれたペンケースや触りたくなる小物、消しゴムなどは置かずに、必要な本数の鉛筆だけ取り出して、残りは机の中にしまうなどの工夫で、子どもが集中できたりします。
2つ目は、時間の整理です。
終わりが見えないまま課題を始めるのではなく、何をどのような手順で進めるのか、どうなったら終わりなのか、終わったらどうすればいいのか、などを事前に子どもに示して課題を始めます。そうすることで、途中で周囲の刺激に注意を向けることが少なくなります。
また、課題をやりきった経験、出来た実感、そしてそれを評価される喜びを積み重ねることで、自己をコントロールする力が身に着くのではないでしょうか。