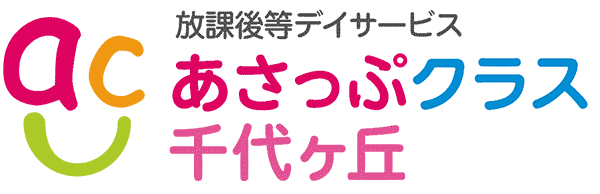今回のブログでは、発達障害の改善へ向けた新しいアプローチ視点と、日常生活の中でのスモールステップに繋げられる様なお話をしたいと思います。(何回かに分けて、掲載する予定)
【発達障害の原因】
発達障害の原因については、世界的規模で様々な研究が進められていますが、まだ全容の解明には至っていないのが現状です。しかし現段階で判明、もしくは疑われている原因について記すだけでも膨大なページを要する程、原因要素は多種多様であり、それが故に対応の難しさも抱えています。
そこで困難の多い現状は受け止めつつも、日常生活の中でのちょっとした気配りや環境設定で行動の改善が期待出来るとされる、最新の?情報をお届けしたいと思います。
【今、「腸」が注目されている】
数か月前、NHKのテレビ番組に於いて、iPS細胞の研究者でノーベル賞を受賞された山中伸弥さんとタモリさんが案内役となり、シリーズで人体の不思議について最新の情報を紹介していました。そのシリーズの中で一番最初に取り上げたテーマが、「腸」でした。ここ数年、腸に関する本が次々と出版され、テレビや雑誌でも「腸内フローラ」という言葉をよく耳にする様になりました。
腸について我々がこれまで抱いて来たイメージは、「食べた物を消化し、その栄養分を吸収した後、不要物を排出する為の器官」といったものではなかったでしょうか?
ところが腸の役割はそれだけではないことが次々と明らかになり、今とても注目されているのです。
【腸は第二の脳】
この様に腸が「第二の脳」と例えられるのには、ちゃんとした訳があります。
人間の免疫力は「脳が外敵を感知し、脳から身体を守る為の指令が送られる」と思いがちですが、実は免疫力の70%~80%は腸が担っているということが分かって来ました。腸内環境が良好な人は、様々な病気に対する耐性が強く、寿命にも影響するとのこと。また、腸は人間の感情や記憶等にも関係していて、例えば便秘や下痢の際、イライラしたり、物事に集中出来なかったり、ネガティブな思考ばかりが浮かんで来る…そんな経験はないでしょうか?
腸内環境を整えることで、毎日の元気・やる気・集中力の土台を築けるのです。
【腸が傷付くと、脳も傷付く?】
腸の表面(腸壁)は、とてもきめ細かなフィルターになっており、人が生命活動を維持して行くのに必要な栄養だけを吸収し、不要な物や毒物等は排除(排出)する機能を備えています。しかし腸が傷付き炎症を起こしたりすると、フィルターの目が粗くなり有害物質の侵入を許し、血液に混じって脳へと運ばれてしまうのです。特に重金属や化学物質は、脳に甚大なダメージを与える場合があるので要注意です。
脳を守る為に、重金属や化学物質を取り込まない工夫も必要ですが、何よりバリアー効果の高い腸内環境を作ることが大切です。
実は現在、発達障害に於ける研究の最先端を行くアメリカで、腸内環境と自閉症との関連性についての取り組みがされているそうです。研究成果に注目したいものです。
次回のブログでは、「腸を傷付ける、意外な犯人」について記載する予定です。