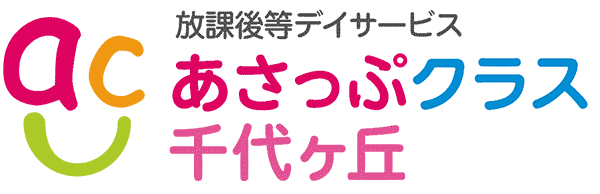LDは「学習障害」と訳されますが、ただ勉強ができないという意味ではなく、話す、聞く、読む、計算するといった学習能力の内、1つまたは複数の能力の習得に困難がみられる状態をいいます。小さいころは目立たず、小学校に上がって、お友達と一緒に勉強するようになってから、「簡単な計算ができない」「日常のおしゃべりは問題ないが音読が苦手」など、苦手な分野が明らかになり、LDと判断されるケースも少なくありません。
これらは、脳の働きの特徴で、障害というよりも個性といえるものです。
これまでLDのある子は、周りの理解や支援もなく、通常の学級で授業を受けていました。
学習内容が難しくなる高学年になるにつれ、どんどん置いていかれてしまいます。
このような状況を踏まえ、2007年度からは、LDをはじめ、高機能自閉症やアスペルガー症候群など、知的の遅れがない子どもたちも、「通級による指導」という制度によってしっかりと支援していくことが出来るようになりました。
文部科学省が全国の公立の小中学校を対象に調査した結果、通常学級に在籍する児童・生徒の約6%に発達障害の疑いがあると報告されています。専門的な診断ではなく教員によるアンケートの結果ですが、1クラスに2~3人はなんらかの発達障害がある子どもがいることになります。
数字を見るかぎり、ありふれた障害だということができます。
LDが起きる原因はまだわかっていませんが、生まれつきの脳の機能障害であり、親の育て方や家庭環境が影響して起こる障害ではありません。しつけや家庭環境が関係していないことは多くの専門家が認めています。
LDが遺伝する可能性も医学的には解明されていません。親や兄弟にLDの人がいても、むやみに心配せず、気になることがあれば、医師や学校の先生に相談しましょう。
LDも他の病気と同じように早期に発見することで、子どもの発達を助けることになります。
最後にLDだった偉人を紹介します。
<まったくしゃべれなかったアインシュタイン>
ノーベル賞学者のアインシュタインは3歳までまったくしゃべらなかったといいます。
学校の成績は数学だけずば抜けて良く、語学は苦手だったようです。
<台本が読めないトム・クルーズ>
俳優のトム・クルーズもLDであることが知られています。
似ているアルファベットの区別がつかず、飛ばし読みをするクセがあるため、台本が読めず、セリフは指で追いながら覚えたといいます。
LD(学習障害)は周りの理解と支援を必要とする個性なのです。