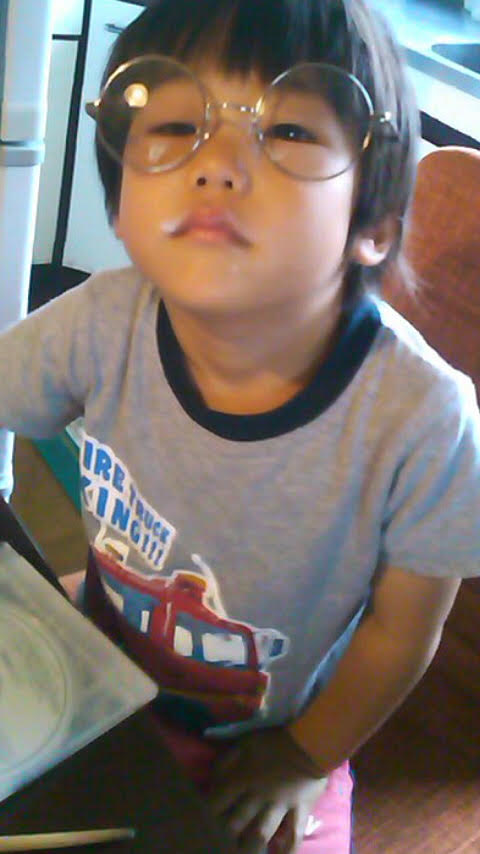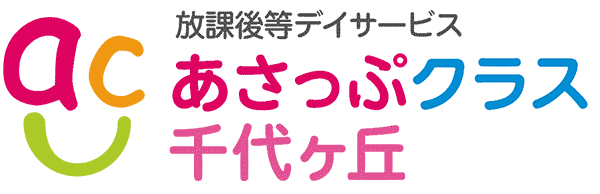【「自閉症スペクトラム」という呼び方】
かつて「広汎性発達障害」と呼ばれていた診断名が、最近では「自閉症スペクトラム(障害)」と呼ばれるようになってきています。これはアメリカ精神医学会が出版している「精神障害の診断・統計マニュアル」(DSM)という出版物の中で記されている診断名が、2013年に変更されたからです。
「DMI-Ⅰ」は戦後間もなく出されていて、兵隊の適性検査や戦地から帰還した兵隊達の診断マニュアルが元になっています。以来、10年~20年に1回程度の変更を重ねて来ました。「DSM-Ⅲ」と「DSM-Ⅳ」において「広汎性発達障害」と呼ばれていたものが、2013年の「DSM-Ⅴ」で「自閉症スペクトラム(障害)」となった訳です。ですから5年前、10年前に出版された書物や、その頃病院で診断を受けた方は「広汎性発達障害」という呼び名が一般的でしたから、「自閉症スペクトラム(障害)」という名称に違和感を持たれるかもしれません。「DSM」の児童版が「ガイドライン」でも示されている「ヴァインランド」です。
腸内環境に関するブログでも述べましたが、この分野での研究、治療、実践活動が圧倒的に進んでいるアメリカからの発信が、世界の流れの主流となっているのです。
【自閉症スペクトラムは特別ではない】
「DSM-5」(数字部分がアラビア数字に変更された)での大きな変化の一つに、「発達障害を連続体(スペクトラム)として捉える」という特徴があります。障害を持った人とそうでない人との間に境界線を引くのではなく、健常者や軽度の自閉症者から重度の自閉症者まで連続的につながっていて、症状の現れ方が違うだけなのだという概念です。
もっと噛み砕いて表現すると、実は大変多くの人が「ちょっと困ったこと(人と話すことが苦手だったり、自己中心的だったり、怒りっぽかったり)」や「ちょっとしたこだわり(毎日やらないと気が済まないことやクセ)」などを持っていて、ただ「社会生活の中でそれほど支障をきたしているわけではない」程度のことなので、本人の自覚や周りの人たちのちょっとした配慮などで、「普通の生活」を営めているのです。
極端な言い方をすると、「完ぺきな人間はいない」ということでしょうか。また別の見方をすると、自閉症の特技は一人一人の個性として捉えることが可能だけれども、本人が「生きづらさ」を感じたり、支援が必要と認められたとき、診断・治療や療育等の様々なサポートを頼れば良いと受け取ることが出来ます。
【大人の発達障害】
こういったテーマで企画されたテレビ番組や本が最近目立つようになってきました。本人も周りの人たちもずっと気づかず過ごしてきて、就職してから、家庭を持ってから、「あれ?もしかして」と思い、診断を受けたら「自閉症スペクトラム(障害)」と告げられた。というケースが増えているそうです。実はこのことも「DSM-5」で述べられていて、自閉症を「幼児期に特有の発達障害ではなく、どの年齢でも発症する(発見される)ことのある発達障害」と定義し直しているのです。
今後ますます、この「自閉症スペクトラム(障害)」という言葉が、日常的に使われるようになっていくと思います。
特別な人だけの問題としてではなく、多くの人たちが自分自身の問題として向き合っていければ、また一歩前進かな
そんな風に思っています。